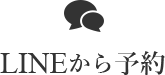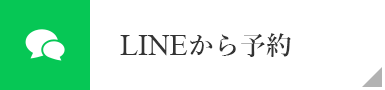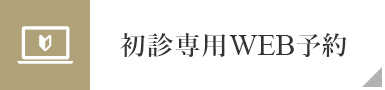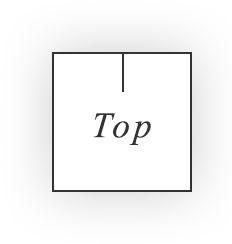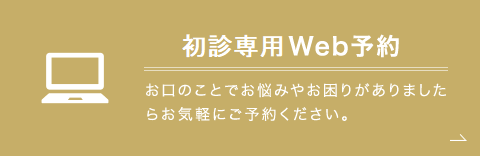歯科恐怖症の方へ
『歯科医院へ行くのが怖い、、』
『歯の痛みに極端に弱い、、』
 歯科医院に恐怖感をお持ちの方も少なくありません。上記のようなお悩みがあることで本当は歯の治療をしたいけど通院することが出来ずにいる方の為に、当院では手術以外の治療にも『静脈内鎮静法』を取り入れております。静脈内鎮静法を施した上で治療を行うとまるで『寝ているうちに治療が終わっている』感覚と近い治療を行うことが出来ます。下記では静脈内鎮静法について詳しくご説明致します。また、短期集中治療にも対応していますので、気になる方は、「短期集中治療」ぺージをご確認ください。
歯科医院に恐怖感をお持ちの方も少なくありません。上記のようなお悩みがあることで本当は歯の治療をしたいけど通院することが出来ずにいる方の為に、当院では手術以外の治療にも『静脈内鎮静法』を取り入れております。静脈内鎮静法を施した上で治療を行うとまるで『寝ているうちに治療が終わっている』感覚と近い治療を行うことが出来ます。下記では静脈内鎮静法について詳しくご説明致します。また、短期集中治療にも対応していますので、気になる方は、「短期集中治療」ぺージをご確認ください。
静脈内鎮静法とは?
 通常の歯科の麻酔は歯ぐきに注射をして麻酔液を注入することで部分的に麻酔を行いますが、静脈内鎮静法は歯ぐきではなく静脈に点滴を使って鎮静剤を投与する方法です。
通常の歯科の麻酔は歯ぐきに注射をして麻酔液を注入することで部分的に麻酔を行いますが、静脈内鎮静法は歯ぐきではなく静脈に点滴を使って鎮静剤を投与する方法です。
通常の部分麻酔とは
何が違うのか?
通常の歯ぐきに注入する部分麻酔は口腔内のみに麻酔が効いている状態ですので、意識はありますが、静脈内鎮静法は静脈に点滴投与するので眠っているようなぼんやりとした意識になります。
静脈内鎮静法のメリット
- 意識が朦朧とした状態になりますのでリラックスして治療を行うことが可能です。
- 1回の治療で多くの箇所を治療することが可能です。
- 痛みが苦手な方や歯科恐怖症の方でも安心して治療を受けられます。
- 治療による刺激での反応が薄くなる為、歯科医師もより集中して質の高い治療を行うことが出来ます。
- 治療後は速やかに麻酔効果が切れますので入院の必要がありません。
静脈内鎮静法の安全性
『全身麻酔は麻酔薬の強力な中枢神経抑制作用により、意識消失、無痛、筋弛緩、自律神経反射や呼吸・循環の抑制を発現するが、精神鎮静法は意識があり、生体の防御、反応や反射が維持されているので安全性が高い』(歯科診療における静脈内鎮静法ガイドラインから引用)とされています。また、当院では麻酔認定医である太田桃子先生が処置に当たります。麻酔認定医とは一般の歯科医師とは異なり歯科治療における麻酔を専門とした歯科医師のことです。歯科麻酔認定医でも一般治療を行いながら歯科麻酔を行っている先生もいますが太田先生は普段は大学病院で麻酔のみをおこなっています。そのため、歯科麻酔における経験は豊富で様々なケースに対応することが可能です。
静脈内鎮静法を用いた
治療後の注意点
- 治療後は麻酔効果が薄れますが患者様によってはまだ麻酔が効いていてフラフラとすることもありますのでそういった場合はクリニック内でお休みいただきます。
- 当日は車・バイクの運転や自転車の運転は控えてください。
静脈内鎮静法の費用について
| 静脈内鎮静法 | 60,000円(税抜) /治療の時間に よって金額の差異が ございます。 |
|---|
※上記に別途治療費が発生致します。
静脈内鎮静法の流れ
1健康状態のチェック
事前に健康状態をチェックさせていただきます。
2ご説明
 当日の処置のご説明と次回以降の治療予定をご説明させていただきます。
当日の処置のご説明と次回以降の治療予定をご説明させていただきます。
3麻酔薬を点滴で投与
麻酔薬を点滴で投与していきます。徐々に深いリラックス状態になっていきます。(フワッとした感覚でそのまま眠ってしまうこともございます。)
4歯科治療
 患者様の反応を確認しながら呼吸状態や心拍数、血圧などモニタリングしながら歯科治療を行います。
患者様の反応を確認しながら呼吸状態や心拍数、血圧などモニタリングしながら歯科治療を行います。
5本日の治療内容・
次回以降の治療の際説明
 当日行った治療内容のご説明・次回以降の治療予定を再度ご説明させていただきます。(専門性が高くなってしまう内容で理解が難しい事もあるため説明が重複することがございます。)
当日行った治療内容のご説明・次回以降の治療予定を再度ご説明させていただきます。(専門性が高くなってしまう内容で理解が難しい事もあるため説明が重複することがございます。)
静脈内鎮静法の
よくあるご質問
静脈内鎮静法をすれば痛みは全く感じなくなりますか?
静脈内鎮静法は痛みを和らげる効果もありますが、最大の効果は眠っているかのような感覚を得られ、気が付いたら治療が終わっているという点です。また、静脈内鎮静法を行って患者様の意識が遠のいてきたら通常と同じく部分麻酔もする為、ほとんど痛みを感じる事はありません。(※効果の実感には、個人差があります。)
静脈内鎮静法は保険適応ですか?
当院では、静脈内鎮静法は自費となっております。
どんな治療にも静脈内鎮静法は可能ですか?
基本的には可能です。ご希望の方は、お気軽にご相談ください。
全身麻酔とは違いますか?
全身麻酔と静脈内鎮静法は全く異なる麻酔法です。全身麻酔は意識が完全になくなり人工呼吸器が必要です。また、入院の必要があります。静脈内鎮静法は意識は無くなりませんし、人工呼吸器も不要です。勿論、入院の必要もありません。
静脈内鎮静法を受けられない場合はどんな場合ですか?
- 妊娠中の方は薬剤が胎児に影響がある可能性がありますのでお受けできません。
- 当日に体調がすぐれない場合は治療を延期することがあります。
- 小さなお子様は受ける事が出来ません。
- 現在、何かしらの病気を患っていて主治医から許可が下りない場合も受ける事は出来ません。
- 現在、服用しているお薬がありそのお薬との影響が出てしまう場合